第44回日本放射線影響学会
平成13年10月29〜31日
大阪・千里ライフサイエンスセンター
シンポジウム−低線量放射線発がん:しきい値とリスク−
講演1:放射線生物学におけるしきい値概念の問題点と落とし穴
佐々木正夫(京都大学)
生物学的効果におけるしきい値作用量とは、「作用原がある一定量に達するまでは起因事象が消去され効果が全く現れない限界量」つまり、「薬物投与や放射線照射で、影響が現れる最少量」のことである。 しきい値を決定するには定量性のある理論的な裏づけが必要だが、最近の放射線発がんにおけるしきい値の取り扱いではそれが満たされていない。
その理由として
- 検定統計量の限界に起因する誤解
◇線量が低くなるに従って、95%検定のためには何十万もの試行(検体の数)が必要になる。 - 観察データに見られるあたかもしきい値のような線量一作用関係の誤解
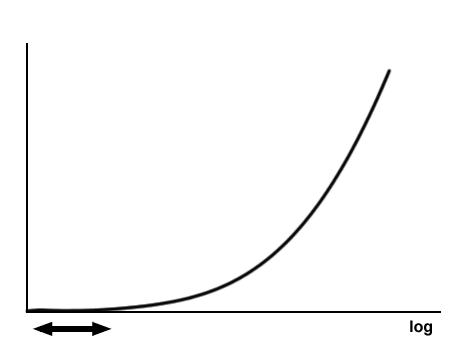
◇一見しきい値のように見えるがゼロとはいえない
- 低線量率効果を低線量のしきい値と誤解
◇両者の背景には全く別の生物学的メカニズムが働いている - 標的組織に対するエネルギー付与の量的・空間的配分の考慮の不足
◇組織による作用効果の違い - 発がんの交絡因子などの潜在的な起因変異の軽視
などが挙げられる。
LNT論争に関してはデータをどう見るかが問題ではなく、その背景に何があるかを研究すべきである。個人的にはしきい値があるとはいわずに研究の発展を促したい。
|
講演2:
|
低線量・低線量率での放射線被爆による発がんリスクに関する疫学データ
|
馬渕清彦(Radiation Epidemiol Branch, NCI, USA)
低線量・低線量率放射線被ばくの影響に関する基礎生物学的な研究の進歩には目覚しいものがあるが、人集団の疫学的データは直接の人体に対する影響の事実を提供する第一の情報源となっている。しかし低線量・低線量率での影響を扱うときには、統計的なパワーの小ささと放射線の影響に対するバックグラウンドノイズの大きさが問題となる。現在われわれが手にすることのできる主な疫学データは原爆生存者と原子力施設従業員からで、いくらかの医療被ばくのデータと高自然放射線地域の住民のデータが加わる。
論点:
- 急性被ばく(0.5-5Sv)に関しては十分な情報を持っているが、この線量での影響はしきい値の議論の対象にはならない。
- 一般的には50mSv以下が対象となる。
問題点:
- リスクを直接推定することは困難なので、外挿が行われる。
- バックグラウンドの線量に近いところの影響を問題にする。
- 検出力の問題が生じる。集団を大きくする必要がある。
- 検出力が十分でない場合には有意義な結果が得られないが、得られたとしてもバイアスがある。
- 交絡因子が問題になる。例えば、地域差・社会経済的要因・生活習慣(喫煙や飲酒)・感染や疾患などを考慮する必要がある。
被爆者データの直接観察から何がわかるか:
- 死亡データの信頼度に限界がある。
- バックグラウンドの変動を考慮する必要がある。
- 傾向を見ることはできる。
最新の原爆生存者の固形がんデータでは:
- 0-0. 1Svで統計的に有意な線量効果の傾向がある。
- しきい値は0Gyである(90%、上限は0.06Sv)
- 線量効果関係が直線的ではないという証拠はない。
しかし疫学データでは結論は難しく、他の方法での評価が必要である。 高自然放射線地域での疫学データに関しては何を対照群にとるかが問題だが、検体数(n)が大きいのでよいデータになりうる。
講演3:しきい値データのレビュー
田ノ岡宏(国立がんセンター、電中研)
放射線発がんの線量効果関係について、しきい値の有無が盛んに議論されているが被ばく時の条件が統一されずに単なる総線量のみで評価されている場合が多い。例えば原爆のような全身一回被ばくと高自然放射線地域の住民のような低線量率慢性(長期)被ばくを線量のみで比較することはできない。そこでこれまでに蓄積されたデータを被ばく条件により分類し、条件ごとの放射線発がんの線量効果関係を整理した。ここで示したいのは発がんモデルや概念はともかく、線量効果の関係が「直線ではない」証拠があるということである。
ラジウム時計盤塗装工の骨髄腫の発生
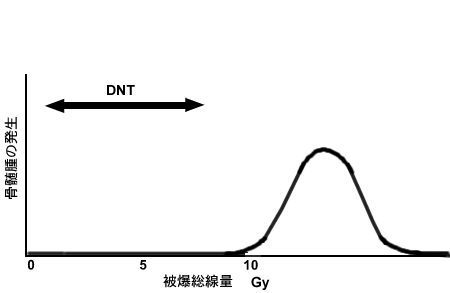
ベータ線照射によるマウスの腫瘍の発生
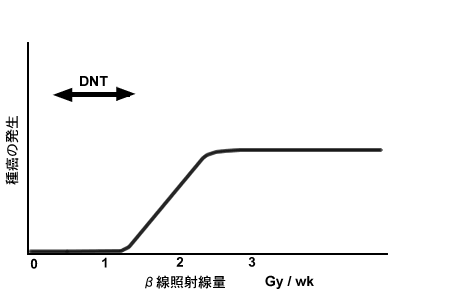
上図のようなデータは数多い。 がんの発生が見られない線量限界をDNT(non-tumor dose)としてチャートにまとめた。
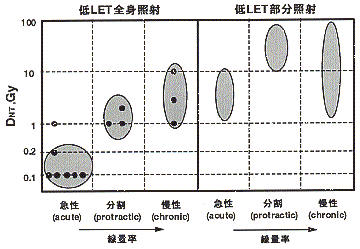
線量効果は考えているよりはるかに大きな幅を持っており、また全身照射より部分照射の方が抵抗性が高い。ヒトと動物のデータをまとめてみても一つの傾向の中に収まる。このような限界線量が生じる理由として、遺伝子の誘導・アポトーシスの誘導・免疫活性の誘導などが考えられる。
講演4:放射線発がんリスクにしきい値がある証拠
近藤宗平(大阪大学名誉教授、近畿大学原研)
人類は数百年間約1mGy/年の自然放射線の中で暮らしてきた。この程度の被ばくに人体はびくともしないはずである。直線仮説を適用するチェルノブイリ放射能汚染(50mSv)による小児白血病は増加するはずだが実際には汚染前後で発症頻度に差はなかった。中国の高自然放射線地域(対照地域の約3倍)での固形がん死の相対リスクは400mSv以上の被ばく群では対照群より明らかにリスクは低い。これはホルミシス効果だろう。
討 論
- 0.3Gy以上ではDSB修復機能は正常に働いていないので、そのような線量での実験は実験のための実験でしかなく、生物学的には意味がないと思われる。また、バックグラウンドに隠れてしまうような状況は問題にしても仕方がない。常識の範囲内に戻すことが大切。
- しきい値があるかどうかが問題で安全の問題にすりかえてはいけない。田ノ岡氏も低線量率の問題にすりかえてはいけない。科学的にはっきりさせる必要がある。
- 胎児の奇形についてのしきい値の有無は現段階では不明。nの数の問題でもう少し多ければ。がんについては原爆データからしきい値があるとはいえない。
- 毎日一生の間被ばくしつづければ、どこかでがんの発生率が上がってくるところがあるはず。しきい値は必ずある。
- DNA修復やアポトーシスの誘導がなければ線量−効果関係は直線的であるかもしれないが、これらの機能があるために直線的でなくなると考えるのはどうか。
- しかしある線量までは完全にDNAを修復し、アポトーシスで除去するという確証はない。
- 何をend pointにするかでしきい値は変わってくる。どういう要因でこのしきい値が出てくるかを明らかにすることが大切。実験動物は均一な群を作るが、ヒトは不均一なのでこの因子を考慮する必要がある。
- (中国の)高自然放射線地域の住民の末梢血DNAの以上は増加している。しかし、がんは増えていない。(DNAの損傷などの)最初の事象は直線的に起こるかもしれないが、その後の(がんに結びつく)事象は別だろう。その理論については7月の京都シンポジウムの最後のディスカッションでいろいろ出たので、それらをまとめていずれ出版する。
- ある線量以下ではDNA修復などが大きく作用し、しきい値様の反応が見られるに違いない。
- 発がんは組織や年齢によって感受性などの差がある。アポトーシスも同様だ。したがって、しきい値がある場合もない場合もあるだろう。これらの違いを明らかにして考える必要がある。疫学的に全体を一つにして捉えるのは難しい。