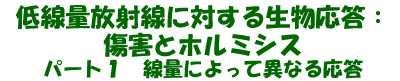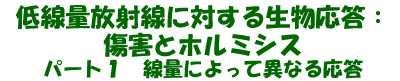|
1.
|
Alberts B, Brey D, Lewis J, Raff M,
Roberts K, Watson JD, eds. Molecular Biology of the Cell. 3rd ed.
New York, NY: Garland Publishing; 1994. |
|
2.
|
Beckman KD, Ames BN. The free radical
theory of aging matures. Physiol Rev. 1998; 78:547-581. |
|
3.
|
Brucer M. Radiation hormesis after
85 years. Health Physics society Newsletter. July 1987:1-3. |
|
4.
|
Editorial. That Healthy Glow. Washington
Post. May 20,2000:B3. |
|
5.
|
Feinendegen LE, The role of adaptive
responses following exposure to ionizing radiation. Human Exper
Toxicol. 1999; 18:426-432. |
|
6.
|
Feinendegen LE, Bond VP, Sondhaus
CA. The dual response to low-dose irradiation: induction vs. prevention
of DNA damage. In: Yamada T, Mothersill C, Michael BD, Potten CS,
eds. Biological Effects of Low Dose Radiation. Excerpta Medica.
International Congress Series 1211. Amsterdam, The Netherlands:
Elsevier; 2000:3-17. |
|
7.
|
Feinendegen LE, Bond VP, Sondhaus
CA, Altman KI. Cellular signal adaptation with damage control at
low doses versus the predominance of DNA damage at high doses. Compt
Rend Acad Sci Paris Life Sci. 1999; 322:245-251. |
|
8.
|
Finendegen LE, Loken M, Booz J, Muehlensiepen
H, Sondhaus CA, Bond VP. Cellular mechanisms of protection and repair
induced by radiation exposure and their consequences for cell system
responses. Stem Cells. 1995; 13:7-20. |
|
9.
|
Finkel T, Holbrook NJ. Oxidants, oxidative
stress and the biology of ageing. Nature (London). 2000; 408:239-247. |
|
10.
|
Friedberg EC, Walker GC, Siede W.
DNA Repair and Mutagenesis. Washington, DC; American Society of
Microbiology; 1995. |
|
11.
|
Hall EJ. Radiobiology for the Radiologist.
5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott; Williams & Wilkins; 2000. |
|
12.
|
Hashimoto S, Shirato H, Hosokawa M,
et al. The suppression of metastases and the change in host immune
response after low-dose total-body irradiation in tumorbearing rats.
Radiation Rec. 1999; 151:717-724. |
|
13.
|
International Commission on Radiation
Units and Measurements. Fundamental Quantities and Units for Ionizing
Radiation. Report 60. Bethesda, MD: ICRU;1998. International Commission
on Radiation Units and Measurements. Microdosimetry. Report 36.
Bethesda, MD: ICRU;1983. |
|
14.
|
Kondo S. Health Effects of Low-Level
Radiation. Madison, WI: Medical Physics Publishing; 1993. |
|
15.
|
Pollycove M, Feinendegen LE. Molecular
biology, epidemiology, and the demise of the linear no-threshold
(LNT) hypothesis. Compt Rend Acad Sci Paris Life Sci.1999; 322:197-204. |
|
16.
|
Sugahara T, Sagan LA, Aoyama T. Low
dose irradiation and biological defense mechanisms. In: Proceedings
of the International Conference on Low Dose Irradiation and Biological
Defense Mechanism, Kyoto, Japan, 12-16 July, 1992. Amsterdam, The
Netherlands: Excerpta Medica, Elsevier, 1992. |
|
17.
|
United Nations Scientific Committee
on Efects of Atomic Radiation. Sources and Effects of Ionizing Radiation.
Annex B. Adaptive Responses to Radiation in Cells and Organisms.
New York, NY: United Nations; 1994. |
|
18.
|
Wilson CTR. J Phys. 1913; 3:529. |
|
19.
|
Wolff S. The adaptive response in
radiobiology: evolving insights and implications. Environ Health
Perspect. 1998; 106:277-283. |
|
20.
|
Yamada T, Hashimoto Y, eds. Apoptosis,
Its Role and Mechanism. Tokyo, Japan: Business Center for Academic
Societies Japan; 1998. |