1) ラドンの生理的作用
ラドンの生理的作用について、これまで次のような知見があり、適応症の機構解明を行う上で基本的な考え方となっている。すなわち、ラドンは不活性ガスであるため、身体のどの構成成分とも反応しない。肺、あるいは皮膚(多くは前者)から入ると血流に入り、身体全体に運ばれる。ラドンは脂溶性が高いので、内分泌腺や神経繊維のような脂肪含有量の高い臓器に蓄積する傾向がある。身体中の滞留時間は短く、50%はわずか15‐30分後に消失する。しかし、この短時間にラドンは組織などと接触し、有益な効果を発揮するものと考えられている。ラドンはα線源であり、その特性から、身体組織内では、約20μmしか進まず、比較的大きなエネルギーが組織に対して与えられるため、一連の複雑な刺激作用が生じる可能性の高いことが指摘されている。
2) ラドン療法の基礎医学的研究
最近、動物実験から培養細胞実験に及ぶ多くの研究により、ヒトで観察される効能について科学的な解明がされつつある。その例を紹介する。
放射線分解によって生体内に生じた少量の活性酸素などのフリーラジカルが、解毒、細胞代謝、ミトコンドリア内でのエネルギー転換、酵素などの蛋白質や生理活性ペプチドの生合成の過程のそれぞれにおいて刺激するものと考えられている。
例えば、スーパーオキシドラジカルの不均化(解毒)を行うsuperoxide dismutase(SOD)の酵素活性が、α線(241Am)、暴露(3.7kBq/l、24時間)によりMDCK培養細胞において増加する(図1)4)。同様に、ラット副腎においてラドン暴露(1kBq/l、663時間)は球状帯のミトコンドリア膜には影響を与えないが、コルチゾルの合成部位である束状帯のミトコンドリアの内膜を有意に増加させることが明らかになった(図2)5)。また、ラットへのラドン暴露(2.2MBq/l、1回1時間・1日2回・6日間)は、痛みの知覚や中枢神経での補助伝達物質としての役割を果たすサブスタンスP(気管支、図3)やカルシトニン遺伝子関連プチペド(脊髄、図4)のようなある種の神経プチペドの産生も賦活化することが報告された6)。これらの研究例はラドン療法により治癒した患者に観察される鎮痛作用や消炎作用などの機構を解明する上で有益な知見となっている。
上記の他、たとえば、ラドンが生体に悪影響を及ぼさない最大放射能濃度(しきい値)の存在を明らかにするため、ラドン吸入と染色体異常発生の関係について、ラドン濃度を変えて動物実験を続けている7)。また、ラドン吸入により肺細胞のDNAは初期損傷を起こすが、これに対して修復という適応応答があることを論理的な分子機構論に基づいた研究が行われている8)。さらに、インスブルック大学医学部のグループでは、細胞膜のイオンチャンネルの挙動や分子細胞レベルでの応答などに着目した紫外線を含む酸化ストレスに対する細胞内の各種挙動に関する研究にも積極的に取り組んでいる。
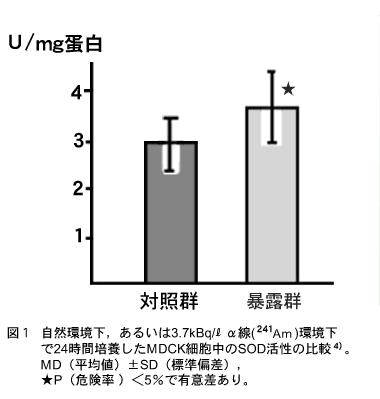
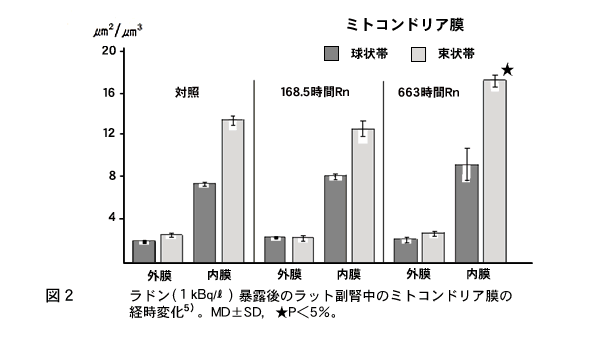
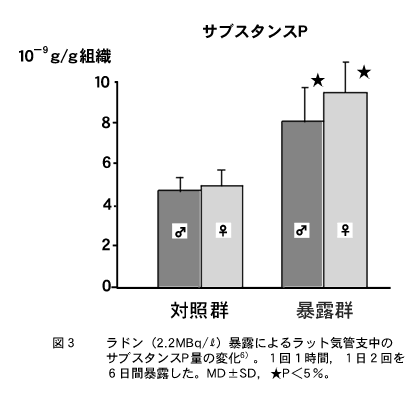
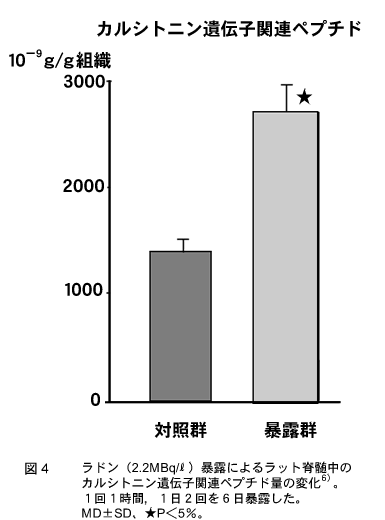
ホームページに関するご意見・ご感想をこちらまでお寄せ下さい。
メールアドレス:rah@iips.co.jp
![]()